| 印象派時代の画家たち |
          |
| 印象派時代の画家たち |
          |
印象派始まりの時代 印象派の中心となる画家たちの多くは、1840年前後の生まれであり、時代の激震をつぶさに見て成長する。1840年代半ばの、資本主義社会の発展のひずみの中で生じた大不況とインフレは、深刻な不安をもたらし、1848年に二月革命が勃発する。晩年を金権政治にまみれて汚れた「市民王」ルイ・フィリップは追い落とされ、臨時政府が共和制を布告する。未来の印象主義者たちは、小さな子供であったが、二月革命とその後の混乱は深く記憶に刻んだものと思われる。 印象派の中心となる画家たちの多くは、1840年前後の生まれであり、時代の激震をつぶさに見て成長する。1840年代半ばの、資本主義社会の発展のひずみの中で生じた大不況とインフレは、深刻な不安をもたらし、1848年に二月革命が勃発する。晩年を金権政治にまみれて汚れた「市民王」ルイ・フィリップは追い落とされ、臨時政府が共和制を布告する。未来の印象主義者たちは、小さな子供であったが、二月革命とその後の混乱は深く記憶に刻んだものと思われる。共和派は、共和国憲法を制定して社会主義的政策を進めようとするが、革命の混乱は収まらず、この混乱に乗じて政権を奪取したのが、ナポレオン三世である。彼は、煽動者を巧みに使って、混乱にうんざりした人々の「英雄待望」に火を付け、時にテロによって反対派を脅し、時に大衆をおだてて躍らせ、きわめて短時日の間に大統領の地位を手にし、4年後の1852年には皇帝にまで上り詰めた。 ヴィクトル・ユゴーが『帝国すなわち恐怖なり』と歌ったナポレオン三世の第二帝政は、まがりなりにも18年間の平和を国内にもたらした。パリでは、その間にセーヌ県知事オースマンの都市改造計画が実行に移された。放射線状の街路や上下水道、ブーローニュの森をはじめとする公園などが整備され、オペラ座が建造されて現在のパリの景観がほぼ定まった。  しかし、その平和は国内における徹底した言論封じ込めと、アルジェリアの完全な征服に見られるような植民地拡大によって支えられていた。ナポレオン三世は、国内産業の増大する生産品を売りさばくために、更なる植民地の拡大を目指し、アルジェリア侵略、ロシアとのクリミア戦争への介入、清朝中国や東南アジア各国への出兵、イタリア統一戦争への軍事援助、メキシコへの出兵など、軍事行動を仕掛けていた。 しかし、その平和は国内における徹底した言論封じ込めと、アルジェリアの完全な征服に見られるような植民地拡大によって支えられていた。ナポレオン三世は、国内産業の増大する生産品を売りさばくために、更なる植民地の拡大を目指し、アルジェリア侵略、ロシアとのクリミア戦争への介入、清朝中国や東南アジア各国への出兵、イタリア統一戦争への軍事援助、メキシコへの出兵など、軍事行動を仕掛けていた。国民に対して統制を強め過ぎたナポレオン三世は、反対勢力の台頭を押さえ切れなくなり、言論統制の緩和など融和政策を打ち出すが、それが共和主義者たちを勢いづかせて、「火に油を注ぐ」結果となり、1860年代末には政権は著しく弱体化する。多数の戦死者を出したメキシコ出兵も失敗し、1867年には総撤退をすることになった。 また、1870年から翌年にかけて、強力なプロシア軍と戦った普仏戦争が、彼の、最後  で最大の軍事的失敗となり、ついに9月、皇帝軍は降伏し、彼はロンドンへ亡命した。 で最大の軍事的失敗となり、ついに9月、皇帝軍は降伏し、彼はロンドンへ亡命した。そして、このナポレオン三世の帝政の末期が、印象派の画家たちにとって、芸術上の自己確立の時に当たっている。第二帝政によりフランスの産業は発展し、急速に豊かな市民階級:ブルジョワジーが形成された。皮肉なことに、繁栄の結果であるブルジョワジーの興隆が、自由主義を生み、帝政を揺るがすに至ったが、印象派の登場も、この新興階級の隆盛が促したものであった。伝統にとらわれない自由な発想、権威に対する反抗は、時代が共有する精神であった。ナポレオン三世は、亡命してロンドンへ去り、共和制の復活が宣言され、プロシアとの戦闘は継続していたものの、新しい時代への予感はたしかにあったに違いない。 皇帝の降伏後、パリの民衆は、バリケードを築いて、包囲する圧倒的なプロシア軍に抵抗し、鼠の肉まで食べるような苦難に耐えながら籠城を続ける。結局、共和国政府の弱腰もあって、翌1871年の初めには鎮圧されてしまったが、この龍城が、世界史上初めての『民衆による民衆のための政治』の実践を試みた3月から5月までの、パリ・コミューンの成立につながるが、政府軍の苛酷な弾圧によって息絶えた。画家クールベはコミューンに参加し投獄された。その際、政府軍によって数万の市民が虐殺される一方、コミューン側も人質の大司教などを処刑したという。印象派の登場は、1874年、この血の惨劇の僅かに3年後のことである。彼らが、当時としてはきわめて革新的な芸術思潮を抱いていたとしても、すこしも不思議ではない。 印象派グループ展の開催  印象派グループの画家たちが知り合ったのは、1863年ころグレールのアトリエで、モネ、シスレー、ルノアール、バジールらが出会い、それにアカデミー・シュイスでかねてからモネと知り合っていたピサロ、セザンヌが合流した。ピサロを通じてモリゾも参加し、彼らはマネやバジールのアトリエ、またカフェで出会い、批評家たちとも親交を結び、戸外に制作に出かけるなど、グループを形成していった。彼らは『バティニョールの仲間たち』といわれた、マネを中心とするレアリスムの流れをくむ人々であった。 印象派グループの画家たちが知り合ったのは、1863年ころグレールのアトリエで、モネ、シスレー、ルノアール、バジールらが出会い、それにアカデミー・シュイスでかねてからモネと知り合っていたピサロ、セザンヌが合流した。ピサロを通じてモリゾも参加し、彼らはマネやバジールのアトリエ、またカフェで出会い、批評家たちとも親交を結び、戸外に制作に出かけるなど、グループを形成していった。彼らは『バティニョールの仲間たち』といわれた、マネを中心とするレアリスムの流れをくむ人々であった。  彼らに対しとりわけ大きな影響を与えたのはマネであった。63年のサロン(官展)に落選し、落選展でスキャンダルを巻き起こした《草上の昼食》、65年のサロンの《オランピア》などの作品で、彼は常に新たな流れの先頭に立ち、その主題の斬新さ、ルネサンス以来の奥行表現を無視したプラン構成、平板に見える人体表現、明暗の際だった色調、生き生きしたタッチなどで若い画家たちを魅了した。彼らの初期の作品には、マネの影響がかなり顕著にみられるが、マネは最後まで彼らのグループ展に参加しなかった。 彼らに対しとりわけ大きな影響を与えたのはマネであった。63年のサロン(官展)に落選し、落選展でスキャンダルを巻き起こした《草上の昼食》、65年のサロンの《オランピア》などの作品で、彼は常に新たな流れの先頭に立ち、その主題の斬新さ、ルネサンス以来の奥行表現を無視したプラン構成、平板に見える人体表現、明暗の際だった色調、生き生きしたタッチなどで若い画家たちを魅了した。彼らの初期の作品には、マネの影響がかなり顕著にみられるが、マネは最後まで彼らのグループ展に参加しなかった。 これらの若者たちは、形骸化したアカデミズムに飽き足らず、サロンでの入選を果たせないため、独自のグループ展を企画した。これが『印象派展』の始まりとなった。第1回展が開かれたのは第三共和政になってからで、キャプシーヌ大通り35番地のナダール写真館で、〈画家、彫刻家、版画家の協同組合〉という名称のもとに、モネ、ドガ、セザンヌ、シスレー、ピサロ、ルノアール、モリゾら30名が165点を出品し、1874年4月15日より1ヵ月間催された。この展覧会を取材した《シャリバリ》紙のルロア記者が、彼らを嘲笑する意味で、モネの《印象、日の出》をもじって〈印象主義者たち〉という言葉を使ったのが、このグループの名称となった。この展覧会はジャーナリズムの興味本位の報道に刺激され、多くの観客がつめかけるなど、話題は提供したものの絵はほとんど売れずに失敗に終わった。 これらの若者たちは、形骸化したアカデミズムに飽き足らず、サロンでの入選を果たせないため、独自のグループ展を企画した。これが『印象派展』の始まりとなった。第1回展が開かれたのは第三共和政になってからで、キャプシーヌ大通り35番地のナダール写真館で、〈画家、彫刻家、版画家の協同組合〉という名称のもとに、モネ、ドガ、セザンヌ、シスレー、ピサロ、ルノアール、モリゾら30名が165点を出品し、1874年4月15日より1ヵ月間催された。この展覧会を取材した《シャリバリ》紙のルロア記者が、彼らを嘲笑する意味で、モネの《印象、日の出》をもじって〈印象主義者たち〉という言葉を使ったのが、このグループの名称となった。この展覧会はジャーナリズムの興味本位の報道に刺激され、多くの観客がつめかけるなど、話題は提供したものの絵はほとんど売れずに失敗に終わった。現在、「印象主義」とか「印象派」とかいう名称を知らない人は少ないだろうが、この名称はこのような偶然から生まれたのである。モネたちは、第3回展から自ら『印象派展』と名乗るようになったが、これは単なる居直りではなく、「印象派」という名称が命名者ルロワの意図とは関わりなしに、彼らが目指すものを端的に示しているように思われたからだろう。そして、自ら名乗ることによって、彼らは、運動体としてのひとつの凝集力を得たともいえる。 以後、『印象派展』は76年、77年、79年、80年、81年、82年、86年と8回を数えたが、彼ら印象派に対する批判は執拗に続き、活動が一般に認められるようになるのは7回展を過ぎてからである。しかし、彼らの示した新鮮なヴィジョンは、徐々にだが確実に人びとの眼と心を染めあげていった。印象派グループはもともと、自由で無審査の展覧会を原則とし、新しい芸術への意欲だけをその共通の方針としていたため、モネ、ルノアール、シスレーらの第1回展以来のグループを保とうとする傾向と、ドガやピサロのように若い人々を参加させようとする傾向の間で対立が生じ、5回展、6回展にはモネ、ルノアール、シスレーが出品せず、また逆に7回展はドガを除く当初の中心メンバー9名だけでとり行われるなどの変化が生じた。また8回展では、ゴーガン、スーラ、ルドンなどが大幅に出品したため、モネらは参加を拒み、印象派のグループ活動は終りを告げる。この『印象派展』に一貫して出品を続けたのはピサロだけであり、セザンヌは1回展と3回展に参加したきりであった。 印象派が革新した三要素 色彩   19世紀になってから色彩と光の原理の研究が進み体系化された。色は三原色のうちの二つを混ぜれば新しい色ができるが、混ぜるほどに明るさは失わる。画面の上に点描で2色を併置し、少し離れたところで見るとこれは混合して見えるから(視覚混合)、必要な色をより明るい状態でとらえられる。明るい画面を得るための執拗な努力は、彼らが戸外制作を行った結果である。すなわち光の中にはそもそも黒は含まれておらず、光の豊かな戸外ではすべてが明るく見える。 19世紀になってから色彩と光の原理の研究が進み体系化された。色は三原色のうちの二つを混ぜれば新しい色ができるが、混ぜるほどに明るさは失わる。画面の上に点描で2色を併置し、少し離れたところで見るとこれは混合して見えるから(視覚混合)、必要な色をより明るい状態でとらえられる。明るい画面を得るための執拗な努力は、彼らが戸外制作を行った結果である。すなわち光の中にはそもそも黒は含まれておらず、光の豊かな戸外ではすべてが明るく見える。構図法   構図法は日本の『浮世絵』と『写真』から大きな影響を受けた。『浮世絵』の極端な俯瞰構図、唐突な画面の切り方、前景に大きなものを配して中景を抜き突然遠景をつなげるやり方、物のボリュームを無視し輪郭で切り抜いた平板な形態など、対象のとらえ方が過去になかった。また『写真』は、四角い枠で視野を切り取ることで大胆な構図が可能になる他、対象を瞬間的にとらえる発想が、印象派の対象のとらえ方に影響を与えた。 構図法は日本の『浮世絵』と『写真』から大きな影響を受けた。『浮世絵』の極端な俯瞰構図、唐突な画面の切り方、前景に大きなものを配して中景を抜き突然遠景をつなげるやり方、物のボリュームを無視し輪郭で切り抜いた平板な形態など、対象のとらえ方が過去になかった。また『写真』は、四角い枠で視野を切り取ることで大胆な構図が可能になる他、対象を瞬間的にとらえる発想が、印象派の対象のとらえ方に影響を与えた。主題   主題は民主主義の時代にふさわしい、いわば『市民による、市民のための、市民的な主題』であった。セーヌ川で船遊びをし、そのほとりのレストランでくつろぐ人々、日傘をさして花咲く野を行く母と子、食卓を囲む一家団欒などのイメージは、近代社会における工業製品の普及やパリなど都市の急速な近代化、鉄道に代表される交通網の発達と旅行の大衆化、スポーツその他のレクレーションの普及など、要するに余暇をもち始め、生活をエンジョイすることを覚え始めた近代市民社会の展開とも密接にかかわっている。 主題は民主主義の時代にふさわしい、いわば『市民による、市民のための、市民的な主題』であった。セーヌ川で船遊びをし、そのほとりのレストランでくつろぐ人々、日傘をさして花咲く野を行く母と子、食卓を囲む一家団欒などのイメージは、近代社会における工業製品の普及やパリなど都市の急速な近代化、鉄道に代表される交通網の発達と旅行の大衆化、スポーツその他のレクレーションの普及など、要するに余暇をもち始め、生活をエンジョイすることを覚え始めた近代市民社会の展開とも密接にかかわっている。具体的には、大通り、駅、カフェとカフェ・コンセール(ミュージック・ホール)、劇場、オペラ、ダンス、公園、競馬場、庭園、鉄道と郊外のレジャー、ボート、海水浴などをあげている。 印象派の中心人物たち   印象派の中心的存在はモネであった。モネが方法的にもっとも徹底していたということだけではなく、彼の不屈の反逆性が仲間たちにとっての心の支えとなったようだ。モネは、ル・アーヴルで過した少年時代からたくみな戯画を描くことで評判が高く、一枚10フランで売れたほどだったが、1858年、18歳のとき、ル・アーヴルの画家ブーダンと会い外光のなかでの写生を勧められ共に画架を並べたことが、彼にとっての決定的な啓示となった。翌1859年パリに出たモネは、グレールのアトリエ仲間とアカデミー・シュイスのグループを結びつける役割を果した。 印象派の中心的存在はモネであった。モネが方法的にもっとも徹底していたということだけではなく、彼の不屈の反逆性が仲間たちにとっての心の支えとなったようだ。モネは、ル・アーヴルで過した少年時代からたくみな戯画を描くことで評判が高く、一枚10フランで売れたほどだったが、1858年、18歳のとき、ル・アーヴルの画家ブーダンと会い外光のなかでの写生を勧められ共に画架を並べたことが、彼にとっての決定的な啓示となった。翌1859年パリに出たモネは、グレールのアトリエ仲間とアカデミー・シュイスのグループを結びつける役割を果した。  中心メンバーのうちの最年長は、1830年生まれでモネより10歳年上のピサロであり、彼の特質は、クールベやコローにつらなるがっしりとした形式感と印象主義的技法との独特の結びつきにある。彼はセザンヌやゴーガンを印象主義に導く役割を果したが、これもこのような彼の特質のせいといえる。 中心メンバーのうちの最年長は、1830年生まれでモネより10歳年上のピサロであり、彼の特質は、クールベやコローにつらなるがっしりとした形式感と印象主義的技法との独特の結びつきにある。彼はセザンヌやゴーガンを印象主義に導く役割を果したが、これもこのような彼の特質のせいといえる。  1834年生まれのドガは、兄貴的な存在であるが、印象派の中心的ジャンルの風景画も静物画もほとんど描かず、もっぱら人物画を描いたという点ですでに異色といえる。加えて印象派風の色調分割も行わない。しかし、踊り子や裸婦などの一瞬の動きをとらえる彼の志向は印象主義の瞬間性と相通じる。また、歴史を描かず、「近代生活」の諸情景を描いたことも印象派との共通する点である。 1834年生まれのドガは、兄貴的な存在であるが、印象派の中心的ジャンルの風景画も静物画もほとんど描かず、もっぱら人物画を描いたという点ですでに異色といえる。加えて印象派風の色調分割も行わない。しかし、踊り子や裸婦などの一瞬の動きをとらえる彼の志向は印象主義の瞬間性と相通じる。また、歴史を描かず、「近代生活」の諸情景を描いたことも印象派との共通する点である。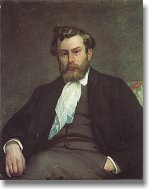  イギリス人画家シスレーは、おそらくモネにもっとも近い資質の持主である。だが彼はモネのようにその視覚的二元論を徹底することなく、一切を光の反映に還元することはなかった。コローを深く愛したこの画家をとらえたのは、光を浴びた風景が生み出す独特の詩情にあった。 イギリス人画家シスレーは、おそらくモネにもっとも近い資質の持主である。だが彼はモネのようにその視覚的二元論を徹底することなく、一切を光の反映に還元することはなかった。コローを深く愛したこの画家をとらえたのは、光を浴びた風景が生み出す独特の詩情にあった。  ルノワールはモネともっとも親しく付きあった仲間であり、よく一緒に写生に出かけた。1869年にセーヌ河畔の遊楽地ラ・グルヌイエールを描いた、二人の作品が残されているが、構図もタッチも酷似していながら、二人の個性の違いもよく分かる。モネの眼が何よりもまず光の効果に反応しているのに対して、ルノワールが捉えているのは、人間や風景が作りあげる根源的な生命感とでも言うべきものだ。この生命感は、ルノワールのなかで刻々に拡大し、ついには晩年の神話的な感じさえする豊麗な裸婦像にいたる。 ルノワールはモネともっとも親しく付きあった仲間であり、よく一緒に写生に出かけた。1869年にセーヌ河畔の遊楽地ラ・グルヌイエールを描いた、二人の作品が残されているが、構図もタッチも酷似していながら、二人の個性の違いもよく分かる。モネの眼が何よりもまず光の効果に反応しているのに対して、ルノワールが捉えているのは、人間や風景が作りあげる根源的な生命感とでも言うべきものだ。この生命感は、ルノワールのなかで刻々に拡大し、ついには晩年の神話的な感じさえする豊麗な裸婦像にいたる。印象派の女性画家たち  印象派絵画は「繊細さ」「自発性」「魅力」など女性性に直結する言葉が多く含まれている。また、現代性を客観的に表象するという装いのもとに、女性は印象派の絵の主題に多く取り上げられている。それら女性の世界の表現をベルト・モリゾ、メアリー・カサット、エヴァ・ゴンザレスら女流画家たちの思い込みによって条件づけられた。 彼女たちの主題が家庭や家族・母子像といったごく狭い私的世界に限定されるのは、行動範囲の狭さを表すと同時に、世間一般の女性画家に対する要求のレベルを表しており、「女性的な色合いや画風であり、男性画家に期待されたものとは別のジャンルの作品だった。 印象派絵画は「繊細さ」「自発性」「魅力」など女性性に直結する言葉が多く含まれている。また、現代性を客観的に表象するという装いのもとに、女性は印象派の絵の主題に多く取り上げられている。それら女性の世界の表現をベルト・モリゾ、メアリー・カサット、エヴァ・ゴンザレスら女流画家たちの思い込みによって条件づけられた。 彼女たちの主題が家庭や家族・母子像といったごく狭い私的世界に限定されるのは、行動範囲の狭さを表すと同時に、世間一般の女性画家に対する要求のレベルを表しており、「女性的な色合いや画風であり、男性画家に期待されたものとは別のジャンルの作品だった。また、彼女たちは経済的にも裕福であり、仲間の絵画の購入や自宅での夕食会の開催など、彼らの活動を支援した功績も大きい。   モリゾは政府高官を父に持ち裕福な家庭に育った。マネのサークルに加わり、マネと似通った様式を用い、何点かのモデルにもなっている。その後、マネの弟と結婚し社会的にも経済的にも立場を安定させ、彼女が絵を描き続けることに好都合な環境を提供した。 モリゾは政府高官を父に持ち裕福な家庭に育った。マネのサークルに加わり、マネと似通った様式を用い、何点かのモデルにもなっている。その後、マネの弟と結婚し社会的にも経済的にも立場を安定させ、彼女が絵を描き続けることに好都合な環境を提供した。モリゾの主題の大半は、もっぱら家庭的なものでブルジョワ社会が女性のものと規定する領域に属していたが、モリゾの芸術は魅惑的な色彩とスケッチ風の気取らない直感的な技法によってできている。   カサットはアメリカの実業家の裕福で教養のある家庭で育った。カサットの描き出すイメージも、モリゾと同様にあくまでも家庭的であったが、彼女の真の才能は人物画とデザインのセンスにあった。それは彼女がドガに近いことで証明している。また、カサツトは未婚で子供もいなかったが、美術史上最も偉大な「母と子」の観察者であった。 カサットはアメリカの実業家の裕福で教養のある家庭で育った。カサットの描き出すイメージも、モリゾと同様にあくまでも家庭的であったが、彼女の真の才能は人物画とデザインのセンスにあった。それは彼女がドガに近いことで証明している。また、カサツトは未婚で子供もいなかったが、美術史上最も偉大な「母と子」の観察者であった。印象派の勝利の時代   1889年、19世紀は暮れかかり、近代という足音が響きだした時期であり、帝国主義の矛盾はヨーロッパに微妙な揺らぎを与え始めていた。そして、この時代こそが、印象派の勝利の時代であった。 1889年、19世紀は暮れかかり、近代という足音が響きだした時期であり、帝国主義の矛盾はヨーロッパに微妙な揺らぎを与え始めていた。そして、この時代こそが、印象派の勝利の時代であった。同時代を代表する1840年に生まれの巨匠モネは、1883年にパリから北西に約65kmの、セーヌ河東岸の美しい村のジヴェルニーに移り住んだ。モネは、ここを新たな生活と創造の本拠と定め、果樹園と農園、そして庭園のある大きな屋敷を借りた。周囲にはのどかな田園地帯が広がり、そこには、《積み藁》《ポプラ並木》など、モネを豊かな創造へと向かわせたさまざまなモチーフが点在していた。 そしてパリ万国博の翌年の1890年、借りていた屋敷と敷地を買い取った。さらに、3年後には土地を買い増し、そこを流れるリュ川と呼ばれる小川を堰止めて、有名な睡蓮の池を造り上げていく。その池にかけた日本風の太鼓橋、水面に浮かぶ蓮の花、揺らぐ陽光や柳の反映などが、晩年のモネに無限のインスピレーションを与え、膨大な《睡蓮》の連作を描かせた。  鉄骨構造技術の偉大なる先駆者アレクサンドル・ギュスターヴ・エッフェルの設計により、1889年に開催されたパリ万国博覧会のシンボル・タワーとして建てられた。完成して空に吃立したエッフェル塔の高さ300mの巨大な姿は、改めて人々の驚嘆を誘うとともに、まさに新しい時代の到来を予告するものであった。 鉄骨構造技術の偉大なる先駆者アレクサンドル・ギュスターヴ・エッフェルの設計により、1889年に開催されたパリ万国博覧会のシンボル・タワーとして建てられた。完成して空に吃立したエッフェル塔の高さ300mの巨大な姿は、改めて人々の驚嘆を誘うとともに、まさに新しい時代の到来を予告するものであった。 版画家リヴィエールは、自分の目でエッフェル塔の成長過程を観察し、新時代を象徴するこの大建造物を、生涯最高の傑作《エッフェル塔三十六景》36枚組の版画セットで制作した。このセットは、葛飾北斎の《富嶽三十六景》にならい、富士山をエッフェル塔に置き換えて構成されたもので、当時、パリを中心に欧米各地で流行をきわめたジャボニスムの代表的な連作である。また、スーラも完成前のエッフェル塔を点描画法により描いている。 版画家リヴィエールは、自分の目でエッフェル塔の成長過程を観察し、新時代を象徴するこの大建造物を、生涯最高の傑作《エッフェル塔三十六景》36枚組の版画セットで制作した。このセットは、葛飾北斎の《富嶽三十六景》にならい、富士山をエッフェル塔に置き換えて構成されたもので、当時、パリを中心に欧米各地で流行をきわめたジャボニスムの代表的な連作である。また、スーラも完成前のエッフェル塔を点描画法により描いている。当初は、万国博覧会の20年後の1909年には取り壊されることになっていた時限的な建造物エッフェル塔をモチーフに、ひとつの時代のパリの表情と空気を見事に表現した。  そして、エッフェル塔の脚下で開催された万国博覧会は、産業文明の進展の祝祭であると同時に、植民地主義−帝国主義の誇らしげな展示場となっていた。19世紀、産業革命の先進国イギリスの後を追って、フランスも植民地を拡大していった。インドシナ、アルジェリアなど、アジア・アフリカの植民地の風俗や風土を紹介するフランス植民地館は大評判であった。1889年のパリ万国博覧会は、帝国主義がヨーロッパにもたらした富、植民地の民衆の血と汗が育てた果実の美味を味わう一大イヴェントに他ならなかった。 そして、エッフェル塔の脚下で開催された万国博覧会は、産業文明の進展の祝祭であると同時に、植民地主義−帝国主義の誇らしげな展示場となっていた。19世紀、産業革命の先進国イギリスの後を追って、フランスも植民地を拡大していった。インドシナ、アルジェリアなど、アジア・アフリカの植民地の風俗や風土を紹介するフランス植民地館は大評判であった。1889年のパリ万国博覧会は、帝国主義がヨーロッパにもたらした富、植民地の民衆の血と汗が育てた果実の美味を味わう一大イヴェントに他ならなかった。会場には、日本も明治維新から間近で産業と輸出の振興を願って、パビリオンを開設し参加していた。ジャポニスム流行の時期でもあり、漆器、陶磁器などの伝統工芸品や盆栽には興味が集まったが、ヨーロッパの人々は、日本を完全な文明国と認めていたわけではなかった。 印象派展以降の印象派 印象派としてのグループ活動を止めてからも、彼らは独自性にかなった制作活動を展開していった。 モネは光の変化をますます瞬間的にとらえるため、対象を限定し、ときに構図を固定し、異なった光の状態を描き分ける連作の世界に入る。 ルノアールは一時、古典主義的な輪郭線の復活を目指すがやがて行き詰まり、再び裸婦を中心とした豊饒な色彩の世界に戻ってゆく。 ドガは人体や馬の瞬間的な動きの表現とその結果生まれる特殊な構図への関心を深める。 セザンヌは水浴をする人々や風景を空間の中に構築的に位置付けようとした。 ピサロだけは息子と同世代の画家たちとともに新印象主義の技法を取り入れてゆく。 印象派を出発点に新たな展開 印象派以後の画家たち 印象主義の後をうけて、1880年代後半から20世紀初めにかけてフランスを中心に活躍した一群の個性的な画家たちのこと。イギリスの美術批評家フライが、フランスの新しい絵画を紹介するために組織した展覧会名〈マネと印象派以後の画家たち〉に由来する。日本では、〈後期印象派〉という訳語はすでに大正期にみられたが、適切とは言えず、〈印象派以後〉と理解した方が適切ともいえる。 〈印象派以後〉の画家たちとは、セザンヌ、ゴーギャン、ゴッホの3人を中核に考えるのがふつうで、彼らはいずれも印象主義の洗礼を受けはしたものの、光を色彩に還元する印象派の感覚主義に対する不満から、新しい方向を切り開こうとした作家であった。 画面の構築性、とりわけ精神性を確立しようとした〈印象派以後〉の画家たちが、多かれ少なかれ、意味内容の象徴化に向かったのは、むしろ自然な成り行きであった。   ピサロの影響を多分に受けていた初期のゴーガンは作品によってはセザンヌよりは印象派寄りであるが、しかしブルターニュのポンタヴェン村に定住したゴーガン、ベルナールとその仲間たちは、印象派のように形態と色彩を分割ないし細分せず、これらを単純化し、印象派には見られない明快な輪郭線でかたどり、対象を平面的に処理することで装飾的かつより表現力に富む様式に到達した。これがいわゆる総合主義で、ブルターニュの農民の素朴な信仰を主題とした1888年の《説教のあとの幻想》は、その宣言ともいうべき記念碑的な作品である。 ピサロの影響を多分に受けていた初期のゴーガンは作品によってはセザンヌよりは印象派寄りであるが、しかしブルターニュのポンタヴェン村に定住したゴーガン、ベルナールとその仲間たちは、印象派のように形態と色彩を分割ないし細分せず、これらを単純化し、印象派には見られない明快な輪郭線でかたどり、対象を平面的に処理することで装飾的かつより表現力に富む様式に到達した。これがいわゆる総合主義で、ブルターニュの農民の素朴な信仰を主題とした1888年の《説教のあとの幻想》は、その宣言ともいうべき記念碑的な作品である。ゴーガンのもう一つの大きな歴史的意義は、彼のプリミティヴィスム(原始主義)である。周知のようにゴーガンは1891年にタヒチを訪れた後、一度帰国し1895年に再びタヒチに出発し、そのままついにフランスに帰ることなく南太平洋の異郷にその生を終えたが、タヒチ時代の彼の芸術と思想あるいは行動は、ヨーロッパ的な伝統と価値観を否定して、異郷の自然と異教の神々にそれに代わるものを求めたという点で未曾有のものであった。   セザンヌもまたゴーガンと同様に印象派から出発しながら、反印象派的な地点に到達した一人であった。初期の厚塗りの、タッチの跡の生々しい、暗い色調の人物画や、ロマンティックな、あるいは劇的な主題によった作品を経て、クールベ、マネ、ピサロなどの影響を吸収したセザンヌは1874年の第1回印象派展に参加するが、この時の出品作《首吊りの家》には、例えばモネの《印象、日の出》の軟調な画面、つまり色は霧と霜にかすみ、形はその輪郭を失って光と大気の中に溶け入るかのような画面に対し、セザンヌのそれは確かに外光派的な明るさはあるものの、目のつんだ織物のような、モネとは一線を画す堅牢なマチエールを見せている。 セザンヌもまたゴーガンと同様に印象派から出発しながら、反印象派的な地点に到達した一人であった。初期の厚塗りの、タッチの跡の生々しい、暗い色調の人物画や、ロマンティックな、あるいは劇的な主題によった作品を経て、クールベ、マネ、ピサロなどの影響を吸収したセザンヌは1874年の第1回印象派展に参加するが、この時の出品作《首吊りの家》には、例えばモネの《印象、日の出》の軟調な画面、つまり色は霧と霜にかすみ、形はその輪郭を失って光と大気の中に溶け入るかのような画面に対し、セザンヌのそれは確かに外光派的な明るさはあるものの、目のつんだ織物のような、モネとは一線を画す堅牢なマチエールを見せている。セザンヌは、印象派の一人として自然との対話を繰り返しながら、同時に過去の巨匠との対話も怠らなかった画家であった。彼の理想は「美術館にある絵のように堅牢な絵を作る」ことであり、それを実現するために画家がなすべきは「自然に従ってプッサンをやり  直す」ことであった。セザンヌは、風景であれ、人物であれ、静物であれ、広い意味での"自然に応用して新しい、"堅牢な芸術を創造することであった。一過性のはかない"印象"を画面にとどめて、それでよしとするのではなく、その印象の消え去った後に残るであろう対象の本質を、 直す」ことであった。セザンヌは、風景であれ、人物であれ、静物であれ、広い意味での"自然に応用して新しい、"堅牢な芸術を創造することであった。一過性のはかない"印象"を画面にとどめて、それでよしとするのではなく、その印象の消え去った後に残るであろう対象の本質を、 構造を、その存在感を画面に実現することであった。 構造を、その存在感を画面に実現することであった。彼の描く女性(多くは妻のオルタンス)は一向に美しくも、愛らしくも、ましてや艶めかしくもない。制作中のセザンヌにとって、モデルが自分の家族あるいは友人か、モデルかは問題ではない。彼がこだわるのは一個の絵画的モチーフとしての人物であって、そこでは自分との人間的関係など、問題にはしていなかった。モデルが少しでも動くと、「リンゴが動きますか」とたしなめたというが、彼にとって絵のモチーフとしては人もリンゴも、その価値は全く等しかった。   ゴーガンを導いたのが、原始への渇望であるとすれば、ゴッホを導いたのは、倫理的なものないしは聖的なものへの渇望である。彼が身を委ねたのが、最初は画商の店員であり、次いで伝道師であり、27歳になってはじめて画家を志したということも、そのあらわれといえる。 ゴーガンを導いたのが、原始への渇望であるとすれば、ゴッホを導いたのは、倫理的なものないしは聖的なものへの渇望である。彼が身を委ねたのが、最初は画商の店員であり、次いで伝道師であり、27歳になってはじめて画家を志したということも、そのあらわれといえる。ゴッホは1886年にパリに出て印象派との触れ合いによって、それまでの暗く重い色彩を解放したが、線(線描、デソサン)には無関心な印象派に対し、初期の彼は、色を使い始める前にオランダの農民や風景を硬質の、力強い線で繰り返しスケッチしている。ゴッホのデソサン様式はアルル時代以後、日本の浮世絵版画、ゴーガンのクロワゾニスムの影響もあって一層個性的な、力強いものとなり、ここに色彩とデソサンの融合した他の追随を許さないスタイルを確立した。1888年の末に精神に異常を来したゴッホは、アルルに近いサン・レミや、パリに近いオーヴェールで療養を続けながら熱狂的に仕事を続けるのだが、1890年の7月、ついに力尽き、自ら命を絶った。 印象派画家の浮世絵との出逢い   印象派からの展開として、ロートレックの存在も見落すことはできない。少年の頃の骨折事故のために下半身の成長が止まったということが、彼が画家を志すひとつの切っかけとなったのだが、やがて、ドガや印象派や浮世絵などの影響のもとに、キャバレーやカフェや娼家などを主題として、新鮮な構図と精妙な素描力と辛殊な観察力とにつらぬかれた作品を描いた。またその石版ポスターは、浮世絵の彩色法や構図法と、ロートレックの固有の感覚とがとけあった見事なもので、ひとつの時代を画した。《ムーラン・ルージュにて》におけるロートレックの熟達の線は、浮世絵と同様見る者に、線が絵画に果す役割を強く印象づけている。また、《デイヴァン・ジャボネ》なる日本という文字を含んだキャバレーのポスターもまた、ジェーンの黒い平坦な衣裳を中心に配して浮世絵版画の手法を効果的に利用している。 印象派からの展開として、ロートレックの存在も見落すことはできない。少年の頃の骨折事故のために下半身の成長が止まったということが、彼が画家を志すひとつの切っかけとなったのだが、やがて、ドガや印象派や浮世絵などの影響のもとに、キャバレーやカフェや娼家などを主題として、新鮮な構図と精妙な素描力と辛殊な観察力とにつらぬかれた作品を描いた。またその石版ポスターは、浮世絵の彩色法や構図法と、ロートレックの固有の感覚とがとけあった見事なもので、ひとつの時代を画した。《ムーラン・ルージュにて》におけるロートレックの熟達の線は、浮世絵と同様見る者に、線が絵画に果す役割を強く印象づけている。また、《デイヴァン・ジャボネ》なる日本という文字を含んだキャバレーのポスターもまた、ジェーンの黒い平坦な衣裳を中心に配して浮世絵版画の手法を効果的に利用している。もっとも、浮世絵の影響を受けたのは、ロートレックばかりではない。浮世絵が、19世紀後半のヨーロッパ美術に、とりわけ印象派の画家たちに及ぼした影響はまさしく決定的なものだ。   マネの《オランピア》のあの平塗りの彩色法は明らかに浮世絵からの示唆によるものだろう。《笛吹きの少年》は、その人物描写の平坦さとフラットな背景とのために「トランプのジャックのように滞っペらだ」と非難されたが一方で、日本の浮世絵版画を効果的に用いているとも評価されている。スペイン絵画と浮世絵との独特の綜合だろう。また、《ゾラの肖像》は、アトリエにゾラを招き肖像を描いたが、この肖像の背景には、おそらく琳派と思われる屏風が置かれ、壁には《オランピア》、ベラスケスの《バッカス》の複製版画と共に、国貞の《大嶋門灘右衛門》の浮世絵版画が飾られている。 マネの《オランピア》のあの平塗りの彩色法は明らかに浮世絵からの示唆によるものだろう。《笛吹きの少年》は、その人物描写の平坦さとフラットな背景とのために「トランプのジャックのように滞っペらだ」と非難されたが一方で、日本の浮世絵版画を効果的に用いているとも評価されている。スペイン絵画と浮世絵との独特の綜合だろう。また、《ゾラの肖像》は、アトリエにゾラを招き肖像を描いたが、この肖像の背景には、おそらく琳派と思われる屏風が置かれ、壁には《オランピア》、ベラスケスの《バッカス》の複製版画と共に、国貞の《大嶋門灘右衛門》の浮世絵版画が飾られている。  ドガの《アプサント》に見られる前面にテーブルを大きく斜めに置いた『くの字形』の構図にしても、浮世絵の影響があると言っていい。また、《フエルナンド・サーカスのララ嬢》にしても、下から見上げた不安定な視点の中に、綱を口でくわえて回転しょうとする女性の姿を中心を外して配置している。画面の中心を柱で断ち切るというような思い切った構図にしても、思いもかけぬ視点の設定にしても、たとえば北斎の作品などに多くの先例を見ることができるものだ。 ドガの《アプサント》に見られる前面にテーブルを大きく斜めに置いた『くの字形』の構図にしても、浮世絵の影響があると言っていい。また、《フエルナンド・サーカスのララ嬢》にしても、下から見上げた不安定な視点の中に、綱を口でくわえて回転しょうとする女性の姿を中心を外して配置している。画面の中心を柱で断ち切るというような思い切った構図にしても、思いもかけぬ視点の設定にしても、たとえば北斎の作品などに多くの先例を見ることができるものだ。  カサットも1890年のパリでの大規模な浮世絵展で歌麿に強い印象を受け、10点のシリーズの版画セットに着手する。あくまで浮世絵版画の表現に近づけるために、ドライポイントで明確な輪郭線をひき、転写した輪郭を基に他の版にアクアチントで色版を起こして多色刷を行った。その主題は母と子を主題とした女性の日常生活であった。《ボート遊び》も中心に母と子を据え、手前の男性の暗い色彩と、母子の明るい色彩を対比させる。そしてボートと帆の曲線で結合する構成を浮世絵と結び付けることも可能である。しかし、一生結婚することのなかった女性の、母性への憧れを、画面の中に見てしまうのだ。 カサットも1890年のパリでの大規模な浮世絵展で歌麿に強い印象を受け、10点のシリーズの版画セットに着手する。あくまで浮世絵版画の表現に近づけるために、ドライポイントで明確な輪郭線をひき、転写した輪郭を基に他の版にアクアチントで色版を起こして多色刷を行った。その主題は母と子を主題とした女性の日常生活であった。《ボート遊び》も中心に母と子を据え、手前の男性の暗い色彩と、母子の明るい色彩を対比させる。そしてボートと帆の曲線で結合する構成を浮世絵と結び付けることも可能である。しかし、一生結婚することのなかった女性の、母性への憧れを、画面の中に見てしまうのだ。  モネの場合は、浮世絵を数多く集め、ジヴェルニーの自分の家の庭に睡蓮の池を作って、そこに日本風の太鼓橋までかけさせたほど、日本に惹かれていたモネは、その晩年の全エネルギーを注ぎ込んだ「睡蓮」の連作について、あくまでも自然の忠実な観察の成果だが、もし自分に影響を与えた先例があるとすれば、それは「昔の日本人たち」だったと述べている。また、彼が第二回印象派展に出品した《日本衣裳の女》などを見れば、彼が日本美術に寄せていた並々ならぬ興味のほどはよくわかる。 モネの場合は、浮世絵を数多く集め、ジヴェルニーの自分の家の庭に睡蓮の池を作って、そこに日本風の太鼓橋までかけさせたほど、日本に惹かれていたモネは、その晩年の全エネルギーを注ぎ込んだ「睡蓮」の連作について、あくまでも自然の忠実な観察の成果だが、もし自分に影響を与えた先例があるとすれば、それは「昔の日本人たち」だったと述べている。また、彼が第二回印象派展に出品した《日本衣裳の女》などを見れば、彼が日本美術に寄せていた並々ならぬ興味のほどはよくわかる。  ルノワールはシャルパンティエなど熱心な日本趣味の収集家がいたが、他の画家たちにに比べて日本美術からあまり影響を受けていない。とはいえルノワールも、日本の屏風、唐笠、団扇などが何度も、意識的に使われている。団扇は中でも目立っており、《読書するカミーユ・モネ》《団扇を持つ少女》のいずれも、小道具として効果を上げている。ここでは一見薄っぺらで頼り無げな団扇は、贅沢でヴォリューム感のあるもろもろのオブジェに取り囲まれ、かえって新鮮に見える。 ルノワールはシャルパンティエなど熱心な日本趣味の収集家がいたが、他の画家たちにに比べて日本美術からあまり影響を受けていない。とはいえルノワールも、日本の屏風、唐笠、団扇などが何度も、意識的に使われている。団扇は中でも目立っており、《読書するカミーユ・モネ》《団扇を持つ少女》のいずれも、小道具として効果を上げている。ここでは一見薄っぺらで頼り無げな団扇は、贅沢でヴォリューム感のあるもろもろのオブジェに取り囲まれ、かえって新鮮に見える。  セザンヌも日本趣味には、冷たい目を注いでいたと言っても良い。だが、自然の与える感動を実現しようと、その対象としてサント=ヴィクトワール山は登場する。標高千メートルのこの岩山は、エクスから見ても、それほど目立った姿ではないが、《サント=ヴィクトワール山とシャトー・ノワール》に描かれた堂々たる山容は、山を極端に拡大し、画面の中心に据えた連作であり、北斎の《富山獄三十六景》を連想させる。 セザンヌも日本趣味には、冷たい目を注いでいたと言っても良い。だが、自然の与える感動を実現しようと、その対象としてサント=ヴィクトワール山は登場する。標高千メートルのこの岩山は、エクスから見ても、それほど目立った姿ではないが、《サント=ヴィクトワール山とシャトー・ノワール》に描かれた堂々たる山容は、山を極端に拡大し、画面の中心に据えた連作であり、北斎の《富山獄三十六景》を連想させる。  ゴーガンもまた、強く浮世絵の影響を受けた画家のひとりである。彼の「綜合主義」も、ステンド・グラスや民衆版画とともに、浮世絵からの示唆があったことだろう。《説教の後の幻影》の画面では、強く単純な人物像と紅色の大地、そして画面の中央を斜に切る樹木は、浮世絵版画の色彩や、一部だけをクローズアップした大胆な構成法を用いている。また、ブルターニュ時代にはバックに浮世絵をかけ、手前にブリミチーフな自作の壷を描いた静物画を描いているが、これは、彼の興味のありようを端的に示している。 ゴーガンもまた、強く浮世絵の影響を受けた画家のひとりである。彼の「綜合主義」も、ステンド・グラスや民衆版画とともに、浮世絵からの示唆があったことだろう。《説教の後の幻影》の画面では、強く単純な人物像と紅色の大地、そして画面の中央を斜に切る樹木は、浮世絵版画の色彩や、一部だけをクローズアップした大胆な構成法を用いている。また、ブルターニュ時代にはバックに浮世絵をかけ、手前にブリミチーフな自作の壷を描いた静物画を描いているが、これは、彼の興味のありようを端的に示している。  ゴッホの場合はさらに熱狂的である。彼は1885年の末にオランダからベルギーのアントワープに出て来たとき浮世絵に接したようだがこれは彼の色彩への開眼のひとつの切っかけとなった。翌年の3月パリに出て日本趣味の渦中にのめりこむ。パリ時代の代表作の《タンギー爺さん》は、背景に浮世絵が飾られており、彼の熱狂ぶりがよくわかる。また、英泉や広重の油絵による模写まで試みている。このような浮世絵の影響は、1888年からのアルル時代に充分に血肉化され、あざやかに開花した。 ゴッホの場合はさらに熱狂的である。彼は1885年の末にオランダからベルギーのアントワープに出て来たとき浮世絵に接したようだがこれは彼の色彩への開眼のひとつの切っかけとなった。翌年の3月パリに出て日本趣味の渦中にのめりこむ。パリ時代の代表作の《タンギー爺さん》は、背景に浮世絵が飾られており、彼の熱狂ぶりがよくわかる。また、英泉や広重の油絵による模写まで試みている。このような浮世絵の影響は、1888年からのアルル時代に充分に血肉化され、あざやかに開花した。というわけで、浮世絵の及ぼした影響にはまことに深く広いものがあるのだが、彼らはただ一方的にそれに身を委ねたわけではない。「浮世絵は、我々が求めていたものを確信させてくれた」というピサロの言葉からもうかがわれるように、浮世絵があれほどの影響力をふるいえたのは、彼らがそれを可能にするほど熟していたからである。かくして、それぞれ個性的なさまざまな合体が成就された。 新印象主義 フランスで19世紀末、1880年代前半から90年代にかけて、まずスーラ、ついでシニャックを中心に展開された絵画運動のことで。〈新印象主義〉という呼称は、美術批評家フェネオンによる。光を色彩に還元しようとした印象派の画家たちは、明るい細かな筆触を並置させることでいままでにない生気に富んだ画面を生みだしたが、その反面で事物の形態は不明確に、構図はしまりのないものになった。 彼らは1884年に結成された独立芸術家協会の創立会員であった。彼らの主催する『独立展(サロン・デ・ザンデパンダン)』の第1回展は同じ1884年に開催されたが、ここでいう”独立”とは官立の美術学校あるいはアカデミスムからの独立であり、その示威運動の場ともいうべき年1回のサロン、および独断専横の支配するそこでの審査制度からの独立であった。要するに自由な展覧会活動をめざして、一定の参加費さえ払えば無鑑査で参加できるこの独立展は、日曜画家のアンリ・ルソーのような型破りの画家にも門戸を開き、当時の画壇の活性化、自由化に多大な貢献を果たした。   スーラはその主要な原因を印象派における色彩並置がいまだ経験的、本能的な段階にとどまっている点に求め、1880年ごろから、ドラクロアの色彩観、ヘルムホルツなどの色彩理論を採用しながら、印象主義そのものを科学的に体系化しようとした。その基本となったのが、色彩は網膜上で混合され『たとえば青と黄は網膜上で結びつき、緑として知覚される』〈視覚混合〉であり、『隣接する色彩は影響しあい、とくに補色どうしは互いの輝きを高めあう』〈色彩の同時的対比〉である。こうして、画面が最高度の輝きを得るために、色彩は当然原色ないし純色に分割されねばならず、そのもっとも効果的な技法として、純色の小斑点を画面に無数に並べていく点描主義が生みだされた。こうした秩序感覚は構図にも向けられ、黄金比をはじめとする、古典的で厳格な幾何学的構図が用いられた。スーラの《グランド・ジャット島の日曜日の午後》はこうした新印象主義の記念碑的な作品である。しかし、彼はこれにあきたらず、画面における線の方向と感情を関係づけようとするアンリの象徴主義的な美学『たとえば、右方向に上ってゆく線は見る者に快感を与える』に共鳴し、それを実制作に取り入れることで新印象主義をより完全なものにしようとしたが、早世した。 スーラはその主要な原因を印象派における色彩並置がいまだ経験的、本能的な段階にとどまっている点に求め、1880年ごろから、ドラクロアの色彩観、ヘルムホルツなどの色彩理論を採用しながら、印象主義そのものを科学的に体系化しようとした。その基本となったのが、色彩は網膜上で混合され『たとえば青と黄は網膜上で結びつき、緑として知覚される』〈視覚混合〉であり、『隣接する色彩は影響しあい、とくに補色どうしは互いの輝きを高めあう』〈色彩の同時的対比〉である。こうして、画面が最高度の輝きを得るために、色彩は当然原色ないし純色に分割されねばならず、そのもっとも効果的な技法として、純色の小斑点を画面に無数に並べていく点描主義が生みだされた。こうした秩序感覚は構図にも向けられ、黄金比をはじめとする、古典的で厳格な幾何学的構図が用いられた。スーラの《グランド・ジャット島の日曜日の午後》はこうした新印象主義の記念碑的な作品である。しかし、彼はこれにあきたらず、画面における線の方向と感情を関係づけようとするアンリの象徴主義的な美学『たとえば、右方向に上ってゆく線は見る者に快感を与える』に共鳴し、それを実制作に取り入れることで新印象主義をより完全なものにしようとしたが、早世した。  スーラのあとを引き継いだシニャックは99年、理論書として《ウージェーヌ・ドラクロアから新印象主義まで》をまとめたが、この運動そのものはすでに終わっいた。『新印象主義』は『点描主義』という単なるスタイルに変質することによってはじめて色彩は対象から自由になり,独自の表現の可能性を与えられ,それはやがてマティスをはじめとするフォーヴィスムの画家たちが画面に原色を爆発させる直接の契機となるのである。 スーラのあとを引き継いだシニャックは99年、理論書として《ウージェーヌ・ドラクロアから新印象主義まで》をまとめたが、この運動そのものはすでに終わっいた。『新印象主義』は『点描主義』という単なるスタイルに変質することによってはじめて色彩は対象から自由になり,独自の表現の可能性を与えられ,それはやがてマティスをはじめとするフォーヴィスムの画家たちが画面に原色を爆発させる直接の契機となるのである。 |